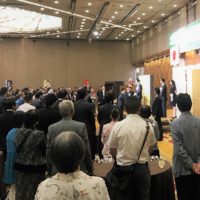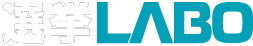-
お電話でのお問い合わせ050-5218-3754
- メールフォーム

30歳からしか出馬できない選挙!?選挙によってルールが違う!

ご自分がどの選挙戦に出馬するか、イメージは固まっているでしょうか。選挙の種類が変わるとルールも変わってきます。
一般に25歳以上の日本国民とされることの多い被選挙権(立候補の資格)ですが、選挙によっては30歳以上でなければならないこともあるのです。
ルールを知らなければ戦う事はできません。まずは各選挙の概略をご説明しますので、出馬を検討している選挙について、再度確認しておきましょう。
Contents
●国政(国会)
▼衆議院議員選挙(総選挙)
・被選挙権(立候補資格) 25歳以上の日本国民
・任期 4年(全員改選)、解散あり
・定数 465人
・選挙方式 小選挙区(289人)・比例代表(176人)並立制
・供託金 小選挙区 300万円、比例代表 600万円(重複立候補の場合は300万円)
・選挙運動期間 12日間
・選挙運動費用の公費負担制度 あり
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送が実施される
▼参議院議員選挙(普通選挙)
・被選挙権(立候補資格) 30歳以上の日本国民
・任期 6年(3年ごとに半数ずつ改選)、解散なし
・定数 242人
・選挙方式 選挙区(146人)・比例代表区(96人)制
・供託金 選挙区 300万円、比例代表区 600万円
・選挙運動期間 17日間
・選挙運動費用の公費負担制度 あり
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送が実施される
●首長
▼都道府県知事選挙
・被選挙権(立候補資格) 30歳以上の日本国民
・任期 4年
・定数 1人
・供託金 300万円
・選挙運動期間 17日間
・選挙運動費用の公費負担制度 あり
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送が実施される
▼政令指定市長選挙
・被選挙権(立候補資格) 25歳以上の日本国民
・任期 4年
・定数 1人
・供託金 240万円
・選挙運動期間 14日間
・選挙運動費用の公費負担制度 あり
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送は実施されない
▼その他の市区長選挙
・被選挙権(立候補資格) 25歳以上の日本国民
・任期 4年
・定数 1人
・供託金 100万円
・選挙運動期間 7日間
・選挙運動費用の公費負担制度 あり
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送は実施されない
▼町村長選挙
・被選挙権(立候補資格) 25歳以上の日本国民
・任期 4年
・定数 1人
・供託金 50万円
・選挙運動期間 5日間
・選挙運動費用の公費負担制度 なし
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送は実施されない
●地方議会
▼都道府県議会選挙
・被選挙権(立候補資格) 25歳以上の日本国民で同議会の選挙権を有すること
・任期 4年
・定数 議会によって異なる
・供託金 60万円
・選挙運動期間 9日間
・選挙運動費用の公費負担制度 あり
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送は実施されない
▼指定都市議会選挙
・被選挙権(立候補資格) 25歳以上の日本国民で同議会の選挙権を有すること
・任期 4年
・定数 議会によって異なる
・供託金 50万円
・選挙運動期間 7日間
・選挙運動費用の公費負担制度 あり
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送は実施されない
▼その他の市区議会選挙
・被選挙権(立候補資格) 25歳以上の日本国民で同議会の選挙権を有すること
・任期 4年
・定数 議会によって異なる
・供託金 30万円
・選挙運動期間 7日間
・選挙運動費用の公費負担制度 あり
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送は実施されない
▼町村議会選挙
・被選挙権(立候補資格) 25歳以上の日本国民で同議会の選挙権を有すること
・任期 4年
・定数 議会によって異なる
・供託金 なし
・選挙運動期間 5日間
・選挙運動費用の公費負担制度 なし
・テレビやラジオなどで政見放送・経歴放送は実施されない
●小選挙区、比例代表など各選挙の選挙方式の違いを知ろう!
各選挙の概略を見てみると、選挙によって方式が違うことが分かりますね。また同じ選挙なのに、小選挙区・比例代表並立制など二つの選挙方式が書かれているものもあります。
それぞれどのような選挙方式なのかについても見て行きましょう。
▼小選挙区制
小選挙区制は、一つの選挙区で一人の議員を選出する選挙制度です。日本の衆議院議員選挙の場合は定数が289人ですから、日本全国を289の選挙区に分割することを意味します。
選挙区の区割りについては、識者で構成された衆議院議員選挙区画定審議会が、国勢調査の結果をもとに審議し、内閣総理大臣が採用して国会の審議を経て決まります。
基本的には人口がなるべく等しくなるように、また大都市以外は市区町村の分割はしないなどの方針により、一票の格差がなるべく小さくなるように区割りされますが、一部に例外も出て来ています。
小選挙区制は、アメリカやイギリスのような二大政党制となりやすく、強力で安定した政権を作りやすい利点があります。
一方で、候補者のうちの一人しか当選しないため死票が多くなり、政党ごとの得票率と実際の議席の数が開きやすく、民意の正確な反映に適していないという欠点もあります。
▼衆議院選挙の比例代表制(拘束名簿式比例代表制)
衆議院の比例代表制は全国を11のブロックに分割し、各政党が獲得した投票数に比例して議席を配分する選挙制度です。ブロックごとにドント式と言う方式で配分することになり、合計で176議席です。
比例代表制では、得票の構成がそのまま議席の配分に繋がるため、さまざまな意見を反映しやすく、死票も最小限で済み、新しい政党が生まれやすいという利点があります。
欠点としては、小さな政党の分立が起こりやすいこと、連立政権となりやすく、議会の意思決定に時間が掛かりがちになることや、政党の役割が重要になって、その幹部に権力が集中しやすくなることがあります。
なお、衆議院議員選挙の場合に限り、候補者は小選挙区と比例代表の重複立候補をすることができます。
▼選挙区制
参議院選挙で用いられる選挙区制は、全国の都道府県を一つの選挙区として(一部例外あり)、その選挙区で1~6つの議席を争います。参議院選挙の選挙区の定数は146ですが、半数を改選するので、一回の選挙では73議席です。
2016年の参議院議員選挙からは、鳥取県と島根県、高知県と徳島県が合同選挙区となっています。
▼参議院選挙の比例代表制(非拘束名簿式比例代表制)
参議院の比例代表制は、全国を一つの選挙区として扱い、各政党が獲得した投票数に比例して議席を配分します。衆議院選挙の比例代表区と同じくドント式で配分され、一回の改選議席数48を争います。
▼その他の選挙
首長選挙は一人を選出する選挙ですので、選挙区という概念はありません。選挙を行う自治体全体で、得票数の多い人が選出されます。
都道府県の議会では市や郡を単位とし、人口に応じて選挙区が設けられ、その選挙区に応じた数の議員を選出します。
市区町村の議会では一般に市区町村全体が一つの選挙区ですが、指定都市などの場合は区が選挙区となったり、ほかにも必要に応じて選挙区が設けられることがあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
それぞれの選挙の概略と、選挙方式について述べてきましたが、いかがだったでしょうか。全体を把握しようとすると、非常に分かりにくい部分が多いかと思います。
また今回お話ししていない供託金や公費負担制度など、普段あまり聞き慣れない言葉も出て来ていますが、これについては機会を改めてご説明したいと思います。
まずはご自身の出馬する選挙について、立候補するための資格を満たしているかどうか、またどのような選挙方式で選出されるのかどうかを確認しておきましょう。
選挙方式によって、とるべき戦略も異なってきます。それぞれの特性を理解して、しっかり対策を練ってくださいね。